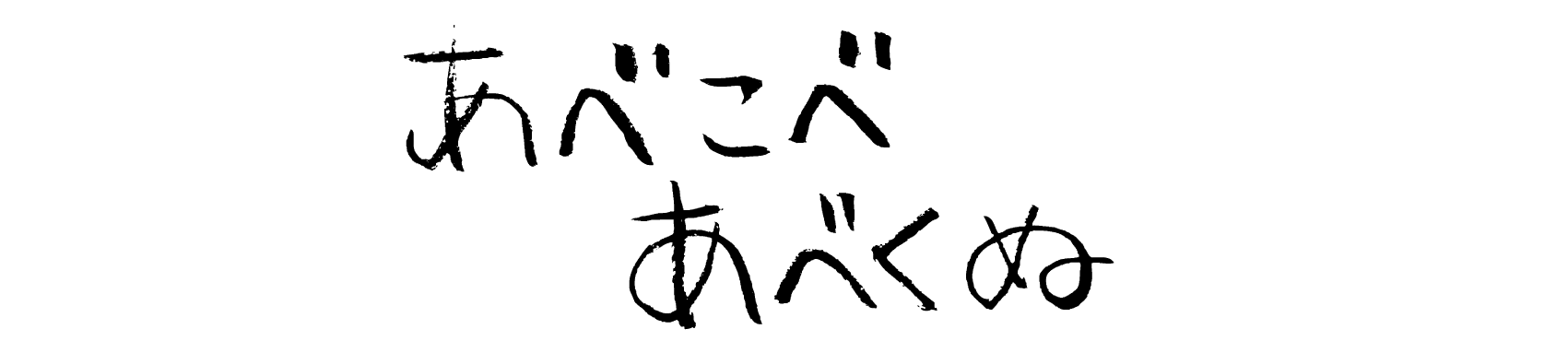「家族葬、どこまでの人を呼んだらいいんだろう?」
ひどい言い方をしますが、呼んだら呼んだで葬儀が大規模になりすぎますし、呼ばなかったら呼ばなかったで人間関係が破綻しかねません。
とはいっても、葬儀に呼ばれなかった人全員が納得する理由を作るのは、ほぼ無理です。
そのなかでも筋の通った、参列者を呼ぶ理由を作るのが重要です。
なぜなら下した決断に、自分たちが納得できるようになるから。
具体的な参列者の選び方を考える前に、ちょっと時間をください。
『誰も傷つかないように』と他人軸で参列者を決めたところで、難癖をつけてくる人は0にはできません。
結局他者をコントロールすることはできないし、さらに他者に大人の対応をしてもらおうだなんて期待をすることは、傲慢にも近いことではないでしょうか。
これまでの人生経験で痛いほど実感しているはずです。
ですが自分たちの意思だけは、自分たちで決められますよね。
だったら他者という不確定要素ではなく、自分たちが納得できる参列者の選び方をしましょう。
葬儀に呼ばれなかったことに激昂する、亡き家族の知人への対応は、葬儀がおわった後もずっと付きまといます。
傷つけて、傷つけられて。
それでも前を向いて生きるには、過去の自分の決断を後悔せず、堂々と受け入れることしかないのです。
もしそれでも参列者の選び方に難儀するようであれば、私たちの参列者の選び方を参考にしてみてください。
スポンサーリンク
家族葬、どこまでの人を呼ぶべき?
私たちは近隣住民と親戚のみ、という決め方をしました。
とりあえず親戚は呼ぼう。
あとは葬儀に呼びたい方々とそうでない方々を、どうロジカルに線引きするかで悩みました。
そこで2つの方法を使いました。
・呼ぶ人を住所でばっさり区切る
・遺言を理由にしてしまう
住所を使って葬儀に呼ぶ人を区切った
住所の区切りを使って、葬儀に呼ぶ呼ばないの線引きをしました。
・家のある1丁目に住む、近隣住民の方のみ呼ぶ
・1丁目以外の人は呼ばない
・仕事でかかわりのあった人も呼ばない
まず最初に考えるべきは、葬儀に呼びたい方です。
その方々をうまく全員呼べないかと思ったとき、住所でのふるいわけが都合よかったんですよね。
応用するなら、上司や部下などといった肩書を基準にするのも良いかもしれません。
客観的な呼ぶ呼ばないの基準があれば、あとで葬儀にお呼びしなかった方に説明するとき、少しでも言い逃れられる余地を残せますよね。
なぜ自分は呼ばれなかったのか、問い詰めらたときにも堂々と伝えられます。
とりあえず呼びたい方をひと通り挙げて、どう一貫した理由を通すか? を考えるとよいでしょう。
理由は後付けしちゃったほうが楽です。
それでもなんで呼んでくれなかったのか、と食い下がられることもあります。
少なくとも私たちにはありましたね。
そんなときは遺言でダメ押ししていました。
『死人に口なし』という乗り切り方
「遺言でこうしてほしい、といわれていたので・・・。」
熱をあげられる方には、そう伝えてしまっていました。
もう亡くなっている人の言うことですから、確認しようがありませんしね。
私たちの場合、葬儀の参列者を決めたのは亡くなった祖父でした。
祖父は「葬儀に呼ばれなかったことについて苦言を呈されたら、全部自分のせいにしていい」と言って、実際に参列してほしい人を遺書に書き残してくれたのです。
残されて生きる遺族を想う気持ち。
本当に最後まで甘えさせてくれた祖父は、とてもかっこよくて素敵だと今でも思います。
入院生活が始まっていて先が長くないとわかっているなら、亡くなる方と相談するのが一番良いです。
生きていてほしいし、本人も懸命に頑張っているなかで死後の話をするのは、本当に心苦しいのですが・・・。
遺族としても亡くなった祖父の意思を汲み取った結果です、と言い切れます。
この事実は葬儀に呼ばれなかった方としては辛く、悲しいことでもありますが、遺族が葬儀に呼ばなかった理由としては納得できますよね。
まとめ:自分本位で考えるぐらいがちょうどよい
・自分の意思だけは自分たちで尊重できる
・他者の反応に迎合した決断は、自分たちを苦しめるだけかも
・葬儀に呼びたい方をあげてから、一貫性を持たせよう
・『死人に口なし』と亡き人に甘えてしまうのもよい
葬儀に呼ぶか呼ばないか。
デリケートな決断を、少しでも後悔なくできるお手伝いができればと思います。